不要オブジェクトの削除について
デザインの中に不要と思われるオブジェクトがございました場合、進行をお止めして確認をさせていただく場合がございます。
印刷に不要なオブジェクトや文字の場合、お客様ご自身で削除をしていただきデータの再入稿をお願いしておりますが、やむを得ず不要データの削除が難しい場合は、ご指示をいただき削除が可能な場合がございます。
こちらで削除をさせていただきました場合は、処理後の内容につきまして確認用のデータをお客様にご確認をいただいてからの進行とさせていただきます。(PDF校正サービスについてを追加させていただきますため、納期が変更になる場合がございます)あらかじめご了承ください。
※オブジェクトの選択ができないデータに関しましては、修正の処理のお承りが出来かねます。
また、選択が可能なデータに関しましても、修正の処理が出来かねる場合がございます。内容によりましては再入稿をお願いする場合がございます。
拡大縮小のご指示について
拡大・縮小のご指示について
拡大・縮小の処理をご希望の場合は、データご入稿画面の備考欄へ明確なご指示をお願いいたします。
塗り足しに関して「全体を拡大処理」」または、拡大率「余白が出ないように拡大」の指示で問題ない場合は、そのまま進行させていただきます。その他のご指示に合わせて処理をする場合は、処理後の内容につきまして確認用のデータをお客様にご確認をいただいてからの進行とさせていただきます。((PDF校正サービスについてを追加させていただきますため、納期が変更になる場合がございます)予めご了承ください。
不要なポイントの除去方法
断裁の際に紙の白い部分が出ないようにするために必要な「塗り足し」部分について。拡大のご指示をいただいた場合でも、デザインや仕上がりに影響が出る場合は、進行を止めて確認させていただきます。
※確認となる例

■備考欄への指示の仕方についての例
-
原寸で仕上がりサイズのセンターに配置。白が出てもそのまま進行
-
左右〇〇mm余白をつけて上下のセンターに配置、上下余白はなりゆきで進行
-
左右を仕上がりサイズまで拡大。塗り足しなしで白がでてもそのまま進行

■塗り足しをつけるために拡大をすると文字が切れてしまう場合の回避例
デザインが仕上がりに非常に近い位置まできている場合、拡大処理をするとデザインが切れてしまいます。その場合は全体を縮小して余白のあるデザインにする方法もご検討ください。

不要データの除去
Illustratorでデータを作成する際、ペンツールや文字ツールで画面上をクリックすると、目には見えませんが、データ内に位置を記憶するアンカーポイントという情報が追加されます。
ペンツールで絵を描きかけてやめたり、文字ツールで文字を入力しようとしてやめたり、を繰り返すと、この余分なポイントがどんどん増えていきます。

▲一見問題なさそうなイラストデータでも...

▲データを確認すると不要なポイントが隠れている事があります
これらのようなゴミデータは印刷時のエラーの原因になります。
アンカーポイントに限らず、トンボの外側等に不要なデータを残したままご入稿されますと、
どれが印刷すべきデータか判別が付かずデータチェックで保留や再入稿になるケースも起こり得ます。
ある程度データが出来上がったら、これら不要なアンカーポイントやデータは削除していただきますと安心です。
不要なポイントの除去方法
不要なポイントは以下の方法で除去します。
Illustratorでのポイントの除去
編集できないように保護されているデータを解除します。
レイヤーパネルから、すべてのレイヤーのロックを外します。

「オブジェクト」メニューから「すべてをロック解除」をクリックします。
(クリックできないようになっている場合は、この手順は不要です)
「選択」メニューから「オブジェクト」→「余分なポイント」を実行します。
画面内に存在する不要なポイントが選択されるので、削除しましょう。

ファイル名の付け方(機種依存文字について)
データを保存するときにつけるファイル名に、機種依存文字などを使用すると「リンク外れ」な�ど思わぬトラブルが発生する場合がございます。
環境依存文字(機種依存文字)
パソコンで使用できる記号に、環境依存文字(機種依存文字)というものがあります。
名の通り機種独特の文字で、例えばMacintosh特有文字を、Windowsの相手に送信した場合、文字は化けてしまいます。
また、Windows特有文字をMacintoshに送信した際にも同様の結果となります。
リンクファイルにこのような特殊な文字を使用していると、送信先で文字が化け「リンク外れ」となりファイルが正常に開けない状態になります。
また全角の文字も化ける原因になる事がありますので、半角英数字がベストと言われています。
ファイル名には機種依存文字を使わないように気を付けましょう。

▼環境依存文字(Windowsの場合)
その他の望ましくない記号
また、パソコンで扱う文字や記号には、独特の役割を持ったものがあります。
例えば、Windows PCで「Cドライブ内のProgram FilesフォルダにあるAdobeフォルダ」を開いてみると、フォルダウインドウには、下図のように表記されます。
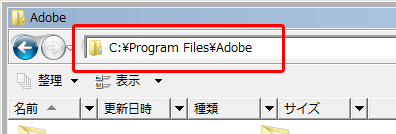
こちらの通り「¥(半角円マーク)」は、フォルダ階層の区切りを示す記号と扱われます。そのため、ファイル名に円マークを含めてしまうと、パソコンは そこが階層の区切りだと勘違いしてしまいファイルを正常に認識できなくなってしまいます。
この円マークのようにファイル名には望ましくない文字や記号があります。特に以下の文字はファイル名には含めないようにご注意ください。
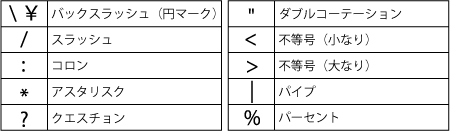
上記以外にも、例えばWebサイトへの流用なども考慮して、ファイル名には記号は(スペースも)なるべく含まず、半角英数で名前をつけていただきますとファイル名によるデータのトラブルが回避できます。
オフセット印刷の表現
オフセット印刷はチラシやパンフレット、雑誌など幅広く用いられている印刷方法です。
カラー印刷の場合、C(シアン)、M(マゼンタ)、Y(イエロー)、K(ブラック)の4色のインキ(プロセスカラーインキ)を使用します。モノクロ印刷はK(ブラック)だけで印刷します。

色は、インキごとに0%~100%の間で濃度を指定します。
CMYKの4色のインキの組み合わせでほとんどの色を再現できます。
データ上で濃度を指定すると下の図のように濃度に応じた均一な色で表現されますが、実際は印刷する機械により表現方法が異なります。
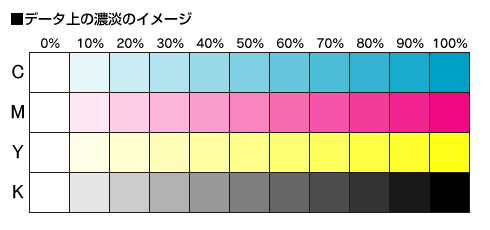
オフセット印刷では、100%部分はインキの均一な状態で表現され、
10~90%部分は、網点(アミ点)と呼ばれる点の集まりで表現します。
決められた範囲の中で、紙の色の部分と、インキの部分の割合で濃淡を表現します。
濃度を上げると網点のサイズが大きくなりインキ部分が多くなるため色は濃くなります。
逆に、濃度を下げると網点のサイズが小さくなり紙の部分が多くなるため薄くなります。
実際にはその濃さの色のインキで印刷するのではなく、点の大きさで紙とインキの割合を調整し、目の錯覚によりその濃さに見えるような表現をしています。
0%は紙自体の色になります。(白は紙の色で、白いインクで印刷するわけではありません。名刺などの普通紙クリームなどは紙自体に色が付いているため、白い部分はありません。)
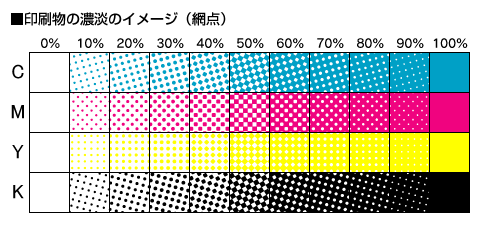
小さい文字に薄い色を指定すると、網点の点同士の間が広く見えるため、オブジェクトの輪郭部分をよく見ると多少ギザギザに見える場合があります。

また、細い線に対して薄い色を指定すると、点線のように見えたり、かすれる場合があります。
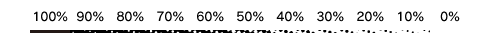
これはオフセット印刷の特徴で避ける事が出来ないため、回避するためには、濃度をある程度濃くしたり、線幅を太くすることが必要になります。
天地と表裏の指示について
両面印刷の場合、表と裏の組み合わせ方をご指定いただく必要があります。
そのために必要になるのが、天地と表裏の指示です。
「天地」とは...印刷データの上下を表す用語です。
印刷データでは、表裏に縦長・横長の絵柄を合わせる場合や、2つ折や4つ折の場合など上下の判別が難しいケースが多くあります。そのため、データ上には「天」・「地」と目印をうち、さらに「天天あわせ」「左天あわせ」といった表裏合わせの指示を行います。
天地のご指示は、トンボの外側や、テキスト、イメージ画像等にて行ってください。
なお、天地についてデータ上で特にご指示が無い場合はデータの上部を「天」、下部を「地」といたします。
天地の指示のしかた
①天天合わせ ~データの表と裏の向き(縦・横)が同じ場合~
裏のデータの上同士(天同士)が合うように両面印刷します。これを「天天合わせ」と呼びます。


②左天合わせ・右天合わせ ~データの表と裏の向き(縦・横)が違う場合~
向きを合わせるためには、裏面を右回りか左回りに回転する必要があります。

一般的には、裏面を右回り(時計回り)に回転し印刷します。
(絵柄の左側が天(上)になるので、「左天」と言います。逆回転を「右天」と言います。)
■左天 裏面を時計回りに回転させた場合。


■左天 裏面を時計回りに回転させた場合。


③天地合わせ ~二つ折りで使用する場合~
折った後の仕上りに合わせて、上下を反転させる必要があります。

このようなデータの場合、裏面を上下を180度反転して印刷します。
絵柄の表面の天(上)と裏面の地(下)を合わせるため、「天地合わせ」と言います。
■天地 裏面を180度回転させた場合。

■天天 裏面を回転させなかった場合。表紙を開くと絵柄が逆になります。

ファイル名にページ数・表裏を入れるのも忘れずに!
両面印刷をする場合は、「表」と「裏」が分かるようにファイル名やデータ上に記しましょう。
※1データで複数ページがある場合、ご指定がなければ奇数ページを「表」、偶数ページを「裏」といたします。
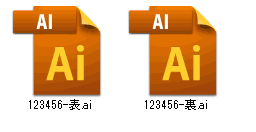
※表裏など複数ページを一つのページ内に作成することはしないでください。
ファイル毎に分けていただくか、ページ毎に作成してください。
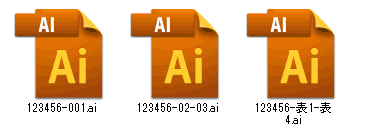
※中綴じ冊子や無線綴じ冊子をする場合は、トンボの外側や、
ファイル名などでページが分かるようにしてください。
グレースケール(K1色)への変換
黒色の文字・罫線・QRコード・各種バーコードは、グレースケールで作成してください。
微量な紙の伸びや印刷のズレで、色の変化や読み取り不良が発生する場合があります。
また、3色及び4色で表現されるセピア・グレー表現やモノクロイメージ画像も同様に色の微細な再現が困難ですので、グレースケールへ変換後の入稿を推奨いたします。
インターネット上で作成したQRコードやバーコードの画像はRGBの黒色であることがほとんどです。
そのRGB画像をそのままCMYKに変換すると、4色掛け合わせのリッチブラックの画像となってしまいますので、下記のようにグレースケールへ変換を行ってください。
また、QRコードが小さすぎると読み取れない場合があります。データチェック時および製造時に読み取り確認は行っておりません。事前にお客様ご自身でQRコードが読み取れるかご確認の上ご入稿お願いします。
1.ダウンロード直後のQRコードの例
RGBでの黒色の数値となっています。

2.「イメージ」-「モード」からカラーモードでグレースケールを選択

3.グレースケールのQRコードの例
K1色の数値となります。

スミベタとリッチブラックについて
スミベタ
スミベタのスミはCMYKの中のK(黒)の事を指し、ベタは100%の濃度の事を指します。つまりスミベタとはK100%の色を指します。
カラーモードをCMYKで作成する場合には、黒い部分は基本的に、K100%で設定します。
スミベタ
黒い部分がK100%以外の色で表現される状態をリッチブラックと言います。
意図的に黒に他の色を混色して深みのある黒を演出することもできますが、設定の仕方により、仕上りが綺麗にならない場合もありますので注意が必要です。
C100%/M100%/Y100%/K100%の設定や、CMYKの総インキ量が320%を超える成分の場合は、インキ量が多すぎるために印刷が不安定となります。印刷物の仕上がりに大きな問題が生じるため、修正していただく必要があります。
また、細い文字や線にリッチブラックを指定すると見当ズレが発生した際に、下図の様に滲んで読みにくくなる場合があります。
また、リッチブラックの上に白い小さい文字や白い線を配置するとつぶれて見えなくなってしまう場合があります。通常、文字や線などにかかわる部分にはK100%のみを指定してください。

ブラックオーバープリント(スミノセ)
印刷では様々な原因で見当ズレが発生することがあります。
見当ズレが発生すると色の境目に他の色が出たり、紙の色の白が出てしまいます。
その為、他の色の上にある小さな文字や線などは読みにくくなってしまいます。
印刷上の黒は理論上、どのような色を加えても黒になる特性を利用し、印刷の機械で自動的にブラックオーバープリント(スミノセ)という処理をします。
ブラックオーバープリントは、黒の下に重なっている色や図柄などを抜き合わせにせずそのまま印刷し、その上に黒を重ねるため、黒の見当ズレが発生しても影響が少なくなります。

当社オフセット印刷の場合
当社オフセット印刷の場合、K100%の文字や図形などのベクトルデータに対して自動的にオーバープリントの処理をしています。
黒に他の色が入っても黒く見えますが、黒に混色する色により、赤味を帯びた黒や、青味を帯びた黒など、混色された色の影響を受けてしまいます。
そのため、黒の下の色が均一であれば混色の影響は目立ちにくいのですが、黒の面積が広く混色された色が複数あり差が大きい場合に、下にある絵柄などが透けた様に見えてしまうことがあります。
この現象を避けたい場合は、K100%の設定が自動的にブラックオーバープリントになる特性を利用し、K100%にC・M・Yの色をいずれか1%でも混ぜること(C1%/M0%/Y0%/K100%)により、ブラックオーバープリントの処理はされずにヌキ合わせの処理となります。

※この黒の透けている部分は説明のために誇張しております。
フォントについて
アウトライン化(グラフィック化)のすすめ
Illustrator、InDesignなどのソフトウェアでは、フォントを図形に変換する「アウトライン化(グラフィックス化)」という機能があります。
図形に変換されていれば、違う環境下でもフォントが有るか無いかを気にする必要はありません。
弊社対応外のフォントを使用した場合、お客様のイメージ通りに印刷することはできません。また、使用しているフォントやソフトウェアにより全く読めない記号の羅列のように文字が化けてしまう場合もあります。

PDFデータでご入稿する場合、エンベッドしていただく必要があります。
エンベッドとは、データの中にフォント情報を埋め込むことです。
エンベッドされていればフォントが無い環境でもフォントのデザインを生かした状態で印刷する事ができます。
画像の解像度について
【データチェック時の粗画像の保留について】
粗画像の保留をご希望の場合は、データご入稿時の「データの仕様」にて「粗画像の場合は保留」をご選択ください。

「粗画像」の基準について
・解像度の確認はしておりませんので予めご了承ください
・お客様からご入稿いただいた印刷用データ上で目視(モニター全体表示)にて確認を行っております。
・画像に含まれている文字などが読めないと判断させていただいた場合、ご連絡させていただきます。
・左の画像を目安にご連絡させていただいております。
「解像度」については引き続き以下をご覧ください。
印刷時に画像の美しさを左右するのは「画像解像度」です。
以下、画像の解像度についてご説明いたします。
ビットマップ画像

デジタルカメラで撮影したデータをPhotoshopで開き、ズームツールでめいっぱいズームアップをすると、画像は小さなマス目(ドットと呼びます)の集合体で出来ていることがわかります。
このようなドットの集合体画像のことを「ビットマップ画像」と呼びます。
このビットマップ画像の品質は、この時のドットのサイズで決まります。

左図の通り、ドットのサイズが小さい方が高画質となり、逆にドットのサイズが大きい方が低画質となります。
解像度とは
先述のドットのサイズを数値であらわしたものが「画像解像度」です。
数値に「dpi(dot per inch)」という単位をつけて「350dpi」や「72dpi」といった表記をします。dpiは、1インチ中にドットがいくつ並ぶサイズなのか?という単位です。
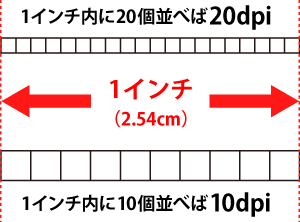
Photoshopの場合は、画素(ピクセル)を基礎単位と扱っているため、dpiではなくppi(pixel per inch)という単位を使用しています。表記は違いますが、��基本的に同じものと捉えていただいてかまいません。
利用目的別の解像度
画像解像度の数値が高いほど、ドットは小さくなるため、画質はきめ細やかで美しい画質になります。
逆に数値が低いとドットは大きくなり、画質は粗くなりますが、その分ファイルサイズが軽くなる、といったメリットもあります。
Webページに掲載する画像は、様々な通信環境を考慮して、なるべく軽量にするため解像度を低く設定します。一方、印刷物の写真には、高い画質が求められるので解像度を高く設定します。
解像度は、以下の数値を基準にして下さい。

※72dpiの画像は、パソコンの画面上で見る分には美しい画像ですが、印刷のクオリティは満たしていません。Webページをプリントアウトすると画像が粗くプリントされるのは、この解像度のためです。web用に作成されたロゴを始めとする画像を、印刷データとして使用する場合は、解像度にご注意ください。
※グレースケール・モノクロ二階調の違い:グレースケールは黒でも濃淡を再現する場合に、モノクロ二階調は真っ黒と真っ白で再現できる画像の場合に使い分けるのが一般的です。
解像度の設定方法と注意点
画像解像度の確認と設定は以下の方法で行います。
Photoshopでの解像度の設定
画像を開いた状態で「イメージ」メニューから「画像解像度」を開きます。
ダイアログ内の「解像度」欄で現在の解像度が確認できます。
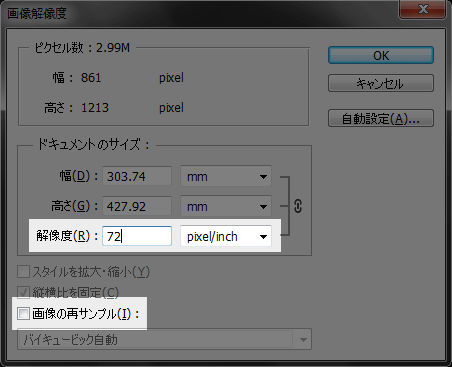
解像度を変更する際には、ダイアログ下部にある「画像の再サンプル」のチェックを外した上で「解像度」欄の数値を変更して「OK」をクリックします。
■「画像の再サンプル」にご注意ください!■
上記で設定している「画像の再サンプル」のチェックは必ず外すようにしましょう。
例えば、解像度を現在の数値よりも高くする場合、チェックのある、なしでは以下の違いがあります。
<再サンプルのチェックが入っている場合>
再サンプルにチェックが入っている場合、Photoshopは現在の画像のドットをさらに細かく分割して解像度を上げようとします。

そのため、画像の縦横サイズは変化しませんが、画質に変化も�ありません。これでは解像度を変更しても意味がないのです。
再サンプルのチェックを入れるのは、すでに解像度が希望の解像度を満たしている際に、画像の表示サイズを変更する場合です。
<再サンプルのチェックを外した場合>
一方、チェックを外した場合は、Photoshopはドットを小さくすることで解像度を高くします。

画質がきめ細やかになり、印刷でも利用できる解像度になります。ただし、全体のドットを縮小するため画像の縦横サイズが小さくなります。
例えば、コンパクトデジタルカメラで撮影した写真は通常72dpiで設定されています。それを印刷物に利用すると、解像度を変更した際に縦横のサイズも小さくなります。
それを考慮して、撮影時にはカメラの設定をなるべく大きなサイズで撮影ができる高画質モードに変えておくといいでしょう。
巻3つ折データの折トンボについて
Illustratorで3つ折の印刷物を作成する場合には、コーナートンボやセンタートンボとは別に、折る位置を示すための折トンボを作成します。こちらでは展開サイズがA4の、巻3つ折チラシを例に、折トンボについてご説明いたします。

巻3つ折データのサイズ配分
巻3つ折印刷物にありがちなトラブルが「紙を3等分で折ってしまう」ことです。
例えば、A4の紙で3つ折を作成する場合に、紙を99mmずつ均等に折り曲げてしまうと、折り畳んだ際に中に巻き込まれる部分がうまく収まらずに、全体が膨らんだような状態になってしまいます。
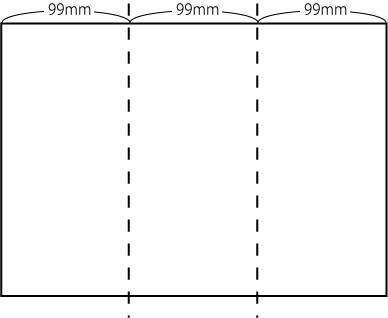

そこで、巻3つ折のデータを作る時には「97mm/100mm/100mm」といったような感じで作成し、中に巻き込まれる部分を少し小さめにすることで、折り曲げた際に、きれいに畳まれるようにします。
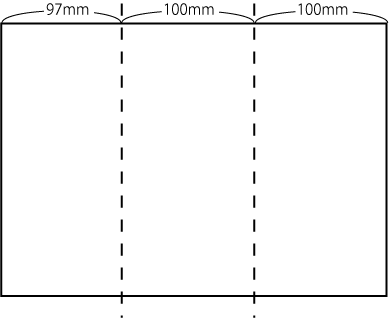

折トンボの作り方
<Illustratorでの折トンボ作成>
ダイレクト選択ツールでコーナートンボ(左上)の内側にある縦線をクリックして選択します。

「オブジェクト」メニューから「変形」→「移動」を実行します。
開いたダイアログで「水平方向」に「100mm」、「垂直方向」に「0mm」を指定して「コピー」ボタンをクリックします。

選択していた縦線が複製され、折トンボが作成されます。

作成された折トンボを選択し、さらに100mm右側に縦線を複製します。

同様の方法でデータ下部にも同じ折トンボを作成して下さい。

また、折トンボの位置は、オモテ面とウラ面で左右対称になることにご注意ください。

折り加工を想定した弊社テンプレートをお使い頂くと、既に折りトンボが入っておりますので デザイン時からスムーズにデータ作成することができます。
トンボと塗り足しについて
トンボとは
「トンボ」というのは、印刷データの外側についている下図のようなマークのことです。
「トリムマーク」と呼ぶこともあります。
トンボは見当合わせ、断裁、折りといった各工程で作業の目安や基準として必ず使われるものです。
センタートンボ、断裁トンボ(コーナートンボ)の他、下図赤丸の折トンボがあります。

「断裁トンボ(コーナートンボ)」や「センタートンボ」は、それぞれ以下のような役割を果たしています。
断裁トンボ(コーナートンボ)
印刷機では家庭用インクジェットプリンターのような「フチなし印刷」ができません。
フチなしの印刷物を作る場合には完成品よりも大きい紙にデータを印刷し、四辺を切り落としてフチなしの状態にします。

その時の切り落とす位置を示しているのが「断裁トンボ」で「コーナートンボ」とも呼ばれます。
センタートンボ
印刷では通常、「シアン」「マゼンタ」「イエロー」「ブラック」の4つの版を用意し、それを重ね刷りすることでカラー印刷を行います。

その時の切り落とす位置を示しているのが「断裁トンボ」で「コーナートンボ」とも呼ばれます。
塗り足し
「塗り足し」は断裁工程に配慮し、背景などを少し大き目に「はみ出して」作った部分の事です。
塗り足しは断裁加工と深く関係しています。トンボを基準にした断裁の作業は、以下のラインで行われます。
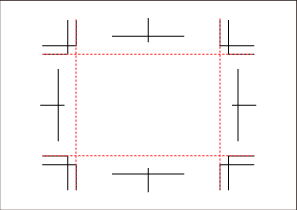
この際、データを仕上がりサイズぴったりで作ってしまった場合、断裁が少しでも外側にずれてしまうと、紙の白が見えてしまい大変見苦しい仕上がりになってしまいます。

そこでデータは、上下左右に3mmずつはみ出すように作成し、万が一断裁がずれても紙の色が出ないようにします。
このはみ出した部分を印刷用語で「塗り足し」と呼び、デザインを作る際には必ず考慮してデータ作成をします。
トンボの外側のラインが、ちょうど3mm大きいサイズのラインなので、このラインに合わせてデータを作成していただきますと安心です。

■ワンポイント~断裁を考慮したデザイン~■
断裁位置に近い文字は、同じく断裁のずれによって文字が切れてしまう可能性がございます。文字や図柄は仕上がり部分より上下左右3mm程度内側(塗り足しから6mm内側)に配置します。
同様に縁取り状のデザインをする場合も、このずれを考慮して縁を太く設けたり、ずれの目立ちにくい絵柄にしておきますと、より一層印刷に適したデザインとなりお奨めです。
【ご注意ください!】
文字やオブジェクトが仕上がりに近い位置に配置されている場合、お客様へ確認をさせていただく可能性がございます。その場合は進行が保留になりますのでご注意ください。
そのままのデザインで問題がない場合はご入稿時の備考欄等でその旨ご記載くださいませ。

【 塗り足しの確認のメールが届いた場合の対処法 】
▶白が出ることを了承する場合
仕上がりの端に白ふちが残ってもよろしければ「白が出てもかまいません」などと記入してご返答ください。 ご入稿時の備考欄等でその旨を明記しするか、メールなどで教えていただければ、塗り足し以外で問題が無ければそのままデータチェック完了となります。
▶白を出したくない場合
背景を広げる等して塗り足しを含んだ状態にデータを修正し、再度データをご入稿ください。
仕上がりサイズについて
お客様が商品としてほしいサイズが仕上がりサイズとなります。
通常の印刷では、仕上がりサイズの用紙に印刷しているのではなく、大きな紙に印刷した後で、『断裁』という作業を行って仕上がりサイズに切揃えています。
仕上がり位置まで色が必要なデザインの場合、断裁時の微妙なズレやデータの微妙なズレにより、白い隙間ができてしまう事があります。仕上がり位置まで色があるデータの場合、必ず3mm分大きく作ってください。(塗り足し)断裁仕上がり位置に近い場所に文字があると、断裁のズレやデータのズレ具合によっては文字が切れてしまうので、デザイン上必要な場合を除いて、仕上がり位置より2~3mm程度内側に作成してください。

折り加工がある場合は、折って完成した商品の大きさが、仕上がりサイズとなります。
折る前の開いた状態のサイズを展開サイズと呼びます。
(二つ折りで仕上がりサイズがA4の場合、展開サイズはA3となります。)

CMYK・RGBのカラーモードについて(カラーの設定)
コンピュータでは、いくつかのカラーモードを扱うことができます。
その中でも代表的��なカラーモードが「RGB」と「CMYK」です。
RGBカラー

RGBカラーは光の3原色です。Red(赤)、Green(緑)、Blue(青)の3つの光を混ぜ合わせて様々な色を作り出します。
身近なところでは、テレビやパソコンのモニターが、このRGBカラーを使って画面を表示しています。
クリエイティブの現場では、Webページのような「画面で表示するデータ」で利用されます。
CMYKカラー

CMYKカラーは、印刷で使うインキ(インク)の色です。シアン、マゼンタ、イエローの色材の3原色にブラックを加えた4色で印刷物の色を表現しています。
ポスターやチラシ、雑誌や書籍などの印刷物は、基本的にこの4色のインクで作られています。 特殊な出力機を使用する場��合を除き、一般的に印刷物のデータを作成する場合は、CMYKカラーで作成されています。
なお、モノクロの印刷物は「グレースケール」や「モノクロ二階調」といった、ブラックだけで印刷する場合が一般的です。
カラーモードを適切に
上記のように、カラーには種類があります。
IllustratorやPhotoshopでデータを作成する際には、適切なカラーモードに設定して制作を行う必要があります。カラーモードが適切でないと、画面で見ている色と印刷結果の色が違う、といったトラブルの原因になります。カラーモードは、それぞれ以下の方法で切り替えます。
Photoshopでのカラーモード変換
画像を開いた状態で「イメージ」メニューから「モード」を開き、使用したいカラーモードを選択します。現在、画像がどのカラーモードを利用しているかは、ファイルタブを見ることで確認できます。
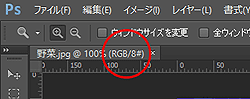
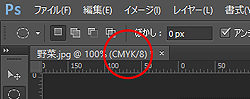
Photoshopの階調は8bit/チャンネルに
「イメージ」-「モード」からカラーモードの設定をする際に、その下部に階調の設定項目があります。8bit/チャンネル・16bit/チャンネル・32bit/チャンネルが選択できますが、ご入稿の際には必ず『8bit/チャンネル』を選択してください。
16bit/チャンネルや32bit/チャンネルに設定した画像をレイアウトしたIllustratorやInDesignデータをご入稿いただくと、画像が意図通りに印刷されない場合がございます。
※Photoshop上で色調補正等を行う場合は、16bit/チャンネル・32bit/チャンネルに変換してから行うことでより精度が高い補正が行うことができますが、補正後には上記のように8bit/チャンネルに再度変換して保存し直してください。

Illustratorでのカラーモード変換
Illustratorでは、新規ファイルを作成する際のダイアログで設定を行います。
プロファイルを「プリント」にすると、自動的にCMYKカラーが設定されます。
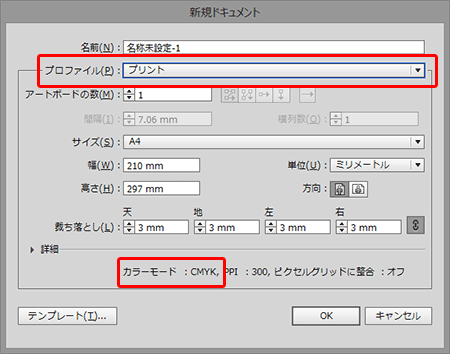
既に、ファイルを作ってしまっていて、現在のカラーモードを知りたい場合には、ファイルを開いた状態で、「ファイル」メニューの「ドキュメントのカラーモード」にて確認、変更が行えます。
MicrosoftOfficeのカラーモード設定
MicrosoftOfficeのアプリケーションでは、カラーモードはRGBの設定になっておりCMYKに変換することはできません。そのため、MicrosoftOfficeのようなOffice系のソフトは印刷データに変換する段階でCMYKに強制的に色変換がおこなわれます。IllustratorやPhotoshopの様に変換結果を鑑みて調整することができないため、画面上と印刷結果の色が異なりやすいデータと言えます。詳しくは次項のワンポイントをご覧ください。
■ワンポイント■

CMYKカラーは、RGBカラーよりも色の表現域が狭く、再現できる色の幅が小さくなります。そのためRGBカラーのデータを、CMYKに変換すると、鮮やかさの幅が小さくなり色がくすみます。これは物理的に避けられない現象で、RGBデータをCMYKデータに変換する場合にはこの色のくすみをより少なく感じさせるため部分的・全体的に色味を細かく調整するなど、画像修正が行われる場合も少なくありません。
前出の通り印刷はCMYKで行われます。印刷データにRGBデータを含んで入稿してしまった場合、下図のように、思ったよりくすんだ色に仕上がってしまう事があります。
特に鮮やかな水色やグリーンなどはくすみが強く出易いので、データの作成時は、それを考慮してデータ作成していただく事をお奨めします。







